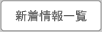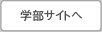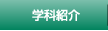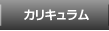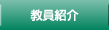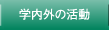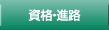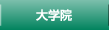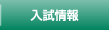3年次後期には全員が研究室に所属し卒業研究を行います。3年次までに身に付けた知識やスキルをもとに研究課題に取り組むことで実践的解決能力が培われる上、研究の楽しさを仲間と分かち合い切磋琢磨することが、国家試験合格への糧になると考えるからです。また、研究を通して身に付ける実行力や発想力は、卒業後の仕事でも発揮できます。
栄養保健学研究室
生活習慣病の予防と健康増進における
生活習慣の在り方を研究。
生活習慣病の予防と健康維持・増進を目指して、食生活と身体活動・運動習慣の在り方について研究しています。最近では、「悪玉コレステロール」、「メタボ」などの言葉が良く聞かれるようになりましたが、正しく意味を理解している人は少ないかもしれません。本研究室では、正しい知識と考え方を持ち、将来、管理栄養士として生活習慣病予防のために適切な助言ができるような基礎づくりを目指します。

公衆衛生学研究室
集団で暮らす人々の健康について、
広い視野で自由に研究を行う。
公衆衛生学の研究対象は人間(集団)です。本研究室では、比較的規模が大きいアンケート調査(疫学調査)や、被験者の生体情報(血圧、体温、心拍数など)を用いて行う実験研究などを行っています。テーマは、おおよそ人々の健康に関するものであれば自由に選べますが、現在は、食に関する健康情報の見方・考え方に関する研究、健康教育の効果に関する研究、日常生活が精神的健康に与える影響などの研究を行っています。

公衆栄養学研究室
地域社会の人々の健康と食生活をテーマとした研究
公衆栄養学研究室では、地域の伝統的な食材に注目し、それらを活かした生活習慣病予防に効果的な食生活について研究しています。また、ロコモティブシンドローム予防について、食生活に着目した研究も実施しています。地域社会の人々の健康維持に貢献できる力を身に付けることを目指します。

調理学研究室
それぞれの思いを形に変える!
研究は学生自身が主体的に能動的態度で取り組み、
目標の達成をめざす。
調理学研究室では、調理に関連する分野の研究を様々な視点でとらえ、学生それぞれが主体的に行動できるようサポートしています。日常的に調理される食事内容に注目し、試験食を開発し摂取後の人体に及ぼす影響に関する研究や調理過程における調理科学的研究,栄養教諭・家庭科教諭向け食物関連分野の調査および教材開発の研究などに取り組んでいます。卒業研究を通して、学生自身の主体性、発想力、計画力、実行力、チームワーク力などを育てます。

給食経営管理論研究室
安心・安全そしておいしい給食提供を目指して
病院、福祉施設、学校や事業所など多くの方が利用する給食施設では、徹底した衛生管理のもと給食提供を行わなければなりません。一方で、給食は食べてもらえてなんぼなので食べてもらえなければいくら衛生管理が徹底されていても意味がありません。給食は絶対においしくなければだめなのです。
本研究室では、安心・安全でおいしい給食を提供するために、効率のよい衛生管理方法の探索というテーマで研究を行っています。

臨床栄養学研究室
人間栄養学の実践。
「人間栄養学」をテーマとし、主に女子大生を対象に食事や運動といった生活習慣のあり方と身体組成の関係性を調べ、健康的なダイエット方法を実現するための研究を行っています。同時に、食・栄養と疾病の関わりに着目し、食事が血糖変動および冷え症の実態に及ぼす影響を明らかにするために、自ら血糖値を測定したり、体表温を計測したりしています。こうした卒業研究を通し、社会で即戦力として活躍するための思考力、プレゼンテーション能力を養います。

食品衛生学研究室
微生物とヒトとの関わりを科学的に解明し、
環境問題や食の安全に貢献することを目的とする。
ヒトの生活と微生物はとても密接な関係性を築いています。代表的な事例として、腸内細菌叢の解析による健康状態チェック、近年話題のプラスチックゴミ問題を解決する微生物生産生分解性プラスチック、微生物が引き起こす食中毒問題などがあります。本研究室では、フードチェーン内で微生物汚染状況の調査、新規微生物を用いた廃棄バイオマスからの高付加価値物質生産などの微生物研究を通して、世間を騒がせている「環境問題」や「食の安全性問題」に取り組んで行きます。

栄養教育論研究室
生活上の食と栄養の課題発見と解決を考える研究。
栄養教育論は、現代の食生活の的確な把握を通じて、健康や栄養状態、食行動や食環境を分析し、適切な栄養指導・栄養教育を展開する方法論の開発を担う研究分野です。当研究室では、小学生から大学生まで若年者や、勤労者を対象とした食行動、食意識、食環境を経年的に調査して実態把握を進め、これを分析して栄養指導や食行動上の課題を指摘し、その解決・改善のための提案を行ったり、様々な食環境整備活動に参加して、将来管理栄養士として働く力を養う実際的な研究指導をしています。

食品科学研究室
食品と食品成分の生体への効果を研究することにより食品に関して科学的に見つめましょう
食品成分に関する基礎・応用研究の実施と、食品自体と食品成分の生体への効果を評価する実験系の確立と効果の評価により、食に関する科学的知識と技術を習得し、豊かな発想力、問題点の発見力、解決策の提案と実行力など、社会の様々な場で役立つ能力を養います。近年、食に関する情報が世の中には溢れ、特に、食品の様々な成分とその効能についての報道、商品がよく見られます。これらを多角的に見つめ、科学的・論理的に評価できるような力を、研究を通して身に付けていくことを目指します。

基礎栄養学研究室
美容から健康長寿まで幅広い観点で
QOLを高める食を考究する
人間の寿命は延びています。そのため、年齢を重ねても美しく綺麗でありたいという欲望が膨らんでいきます。加齢の進行を如実に映し出す鏡が「皮膚」の変化であり、美容上の観点からも、その防御や改善に対する関心がとても高くなっています。基礎栄養学研究室では、「皮膚」という臓器に着目し、その老化メカニズムと食の視点からみたアンチエイジングについて研究しています。

生化学研究室
「細胞レベルの老化」の研究を通し、
「食」の面から健康寿命の延伸を目指します。
加齢にともない「老化した細胞(老化細胞)」が身体に蓄積していきます。老化細胞は様々な液性生理活性因子を放出するSASPという現象を引き起こします。近年、老化細胞の除去やSASPの抑制が老化および様々な疾患の発症を遅延させることが明らかになってきました。生化学研究室では、SASPを抑制する食品・天然物由来因子の探索とSASP発現のメカニズムの解明を目指した研究を通して、探究心を持ち科学的に問題を解決する能力を養います。

卒業研究発表
学びの集大成。研究成果を本格的に発表!
1年間取り組んできた研究成果をまとめ、発表します。各研究の目的や方法、結果を来場者に報告。相手にわかりやすく伝えるために重ねた準備は、社会で求められるプレゼンテーション能力の養成にもつながっています。